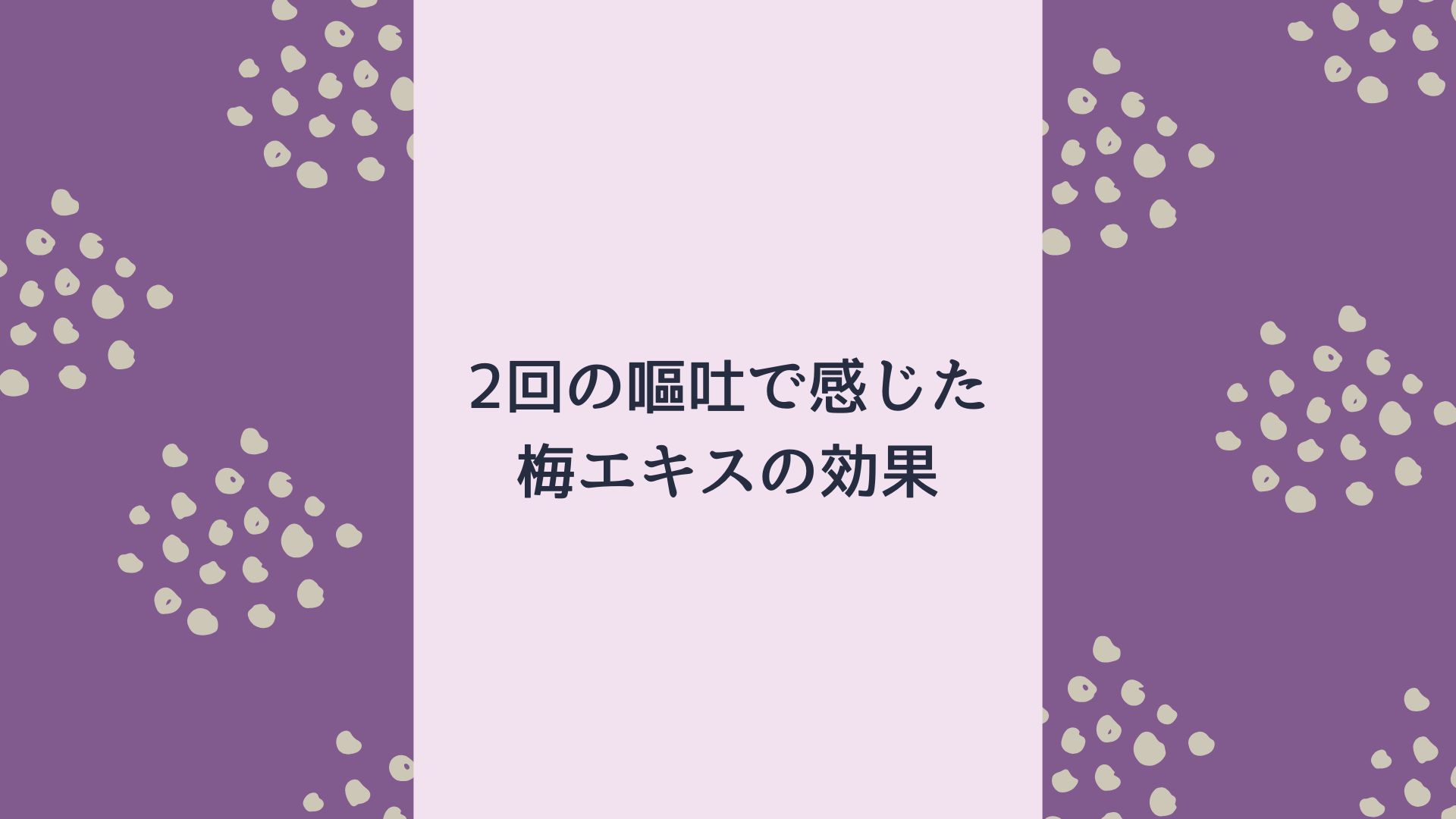様々な効果から、家に一つ常備しておけば安心という梅エキス。
今年はついに、初めて作ってみました。
そしてその完成から数日後。
さあ、試してみて!と言わんばかりに、子どもから謎の嘔吐風邪をもらいました。
ちょうど、その半年前にも、謎の嘔吐と下痢に見舞われていた私。
こんなに効果を試せる機会はないわ・・・
今回は、梅エキスを知るきっかけになった東城百合子さんの本からの梅エキスの効果について。
そして、梅エキスがなかった胃腸炎(?)と梅エキスありで過ごした胃腸炎(?)の経過の違いをお伝えします。
結論は、「梅エキスがあった方が回復は早かった」です。
それでは、まずは梅エキスについてからスタートしていきます。
梅エキスってどんなもの?
まずはじめに、梅エキスについてお伝えします。
梅エキスとは、青梅をすり下ろして絞った後、煮詰めて作るエキスのことです。
自分で作ることもできますし、健康食品店やネットでも売られていますね。
少量摂取するだけで、いろいろな効果があると言われており、戦争中に亡くなる方はほとんどが病死だった中、和歌山の梅の産地の方は、梅エキスを持っていたので、助かった方が多かったという話もどこかで見かけました。
それくらい、効果があるということですね。
例えば、私が持っている、東城百合子さんの本には、以下のように書かれています。
殺菌作用もあり腸内の有効な細菌を育て雑菌を殺しますから、腸の一切の病気に効きます。
腹痛・胸やけ・下痢・便秘・高血圧・低血圧・心臓・腎臓・肝臓・糖尿等によく、子どものある家では必ず常備してほしいものです。
「家庭でできる自然療法 誰でもできる食事と手当法」 東城百合子より
他にも、めまいやアトピーなどの項目にも梅エキスは出てきますし、まだ、私が見ていない病気のところにも載っているかもしれません。
梅エキスの作り方
ザックリいうと、梅エキスは、梅を大根おろしのような状態にして絞り、その液体を煮詰めてできあがります。
東城百合子さんの本にも作り方は載っています。
ただ、手ですりおろすことの大変さと、どのくらいまで煮詰めるのかがわからないこともあり、気になっていたものの、作るには至りませんでした。
そこで出会ったのが、たまたま寄った本屋さんで見かけた梅仕事の本でした。
梅エキスの作り方が載ってる!!
そして、すりおろさなくてもいいのね!
この本には、梅エキスだけでなく、ジップロックでできる梅干しの作り方や、ジャムからシロップまで、いろいろと載っています。
しかし、本を読みつつでも、最後の状態がこれでいいのかな?
気になって、作り終えた後にYouTubeを見てみたら、作り方動画がいろいろ出ていたので、こちらもよかったら参考にしてみてください。
梅エキスなしで過ごした1回目の謎の嘔吐と下痢
2回の嘔吐を経験して分かったことは、どちらも症状が出る前に、予兆はありました。
それは、いつも食べてるような量でも、「もういらないな」と感じることです。
おなかがいっぱいでもなく、食欲がないという感じでもなく、食べてる間に「もういらない」と。
何かで見たのですが、嘔吐するようなときは、胃のキャパが、お茶碗からおちょこくらいの大きさになっているので、入りきらなくて吐いてしまうそうです。
あとで思えば・・・という、些細な違和感だし、もうその頃にはリバース確定状態かもしれないので、本当にあとで思えば・・・なんですが。
違和感を感じつつ過ごした1日の後に嘔吐
- 昼ご飯のレトルトハヤシライスが多く感じた
- 夕方、めまいとのぼせ(商業施設の暖房のせい?)
- 夜ご飯の時でもまだハヤシライスが残っている感じ
- 食べられるけどおいしくない
- 夜中に気持ち悪さで目が覚めてリバース×3
- おなか痛ーいと思いながら寝る
嘔吐2日目
- 朝から下痢
- 出し切ったら治るだろうと、お茶をがぶがぶ飲みながら過ごす
- 昼過ぎごろから頭痛
- 夕方から吐くものはなくなっているのに何回も吐く
- 下痢も出したいけれど出るものがない?という感じ
- 夜ネットで調べて五苓散という漢方を飲む(しぶり腹にはダメと書いてあったのが気になったけど、吐き気と頭痛がひどくて、そこはスルー)
- やっと吐き気が落ち着いて寝る
4日目に病院へ
3日目は日曜だったので五苓散を飲みながら家でしのぎ、4日目に病院へ。
2日目からの症状は、水分はあるけど必要なところにまわっていなくて、脱水だっただろうから、五苓散でよかったとのこと。
おなかの風邪?食あたり?原因ははっきりわからず。
とりあえず、「おなかはまだ動いてないから、おなかがすいてもガツガツたべたらあかんよ!」というお言葉とともに、胃薬や整腸剤をもらって、病院を後にしました。
下痢の復活
ところで、五苓散の注意書きの中で、気になっていた「しぶり腹には使わないように」という一文。
五苓散を飲み始めてから、下痢も止まっていました。
4日目にはちょっと楽になっていたのですが、五苓散をやめて、病院からの薬に切り替えたところ、夜になって下痢が復活。
なんだかスッキリしなかったのは、毒素ができれていなかったようです。
腹痛も始まり、子どもたちのご飯を出した後、この日は早々に休みました。
5日目以降
油物が怖くて、週に4日は鍋、他は野菜スープなどあっさりしたもので過ごしていた日々。
本当にこの腹痛はなおるのだろうか・・・と不安になりながら過ごしていました。
でも、一週間を過ぎたあたりから、少しずつ普通の食事も食べれるように。
やれやれと思ったら、今度は子どもがインフル。
この状態で勝てる気がしねぇ・・・
と気持ちが負けていたからか、嘔吐から10日目には高熱。
なんとかお正月には、通常運転に戻すことができましたが、半月近くはスッキリしませんでした。
半年後、小学校で流行っていた謎の嘔吐をもらう
そろそろ梅エキスを作ろうかと思っていた六月の初め、娘が2回嘔吐しました。
翌日に梅エキスを作り、1日2回ほど飲んでもらっていたところ、娘はそこで終わりました。
そして、私は予防にと梅エキスを1日1回舐めていました。
でも、量が少なかったのか、時すでに遅しだったのか、娘の嘔吐から4日後の夕方、3回リバースしてしまいました。
この時も、思い返せば朝ごはんを少し残し、昼ご飯も、欲しくないな・・・と少なめで、食欲がありませんでした。
嘔吐の後は、梅エキスを舐めて、脱水にならないよう、OS-1を少しずつ飲んですごしました。
嘔吐翌日
37.5℃の熱があったものの、わりと元気だったので午前中は一通りの家事。
とはいえ、まだ気を抜けないので、早々に切り上げて、10時前には休みました。
昼前に起きたら、また頭痛。
やってしまった・・・
昨日の夜はあんなに気を付けていたのに、こまめに水分を取ることをすっかり忘れていました。
そのあとは、少し多めに飲んだのですが、急だったからか腹痛とまた吐き気。
昼過ぎに五苓散を飲んで、頭痛や吐き気はやっとおさまり、なんとか夕方の家事はこなせました。
この日は1日体温は37.5℃~38℃越えをウロウロ。
ご飯も食べていません。
嘔吐後3日目
そして3日目。
熱も下がり、おなかもわりと普通な午前中。
とはいえ、多少のムカつきや胃痛はありました。
でも、そのたびに梅エキスを少し舐めるとおさまるので、お昼のおやつには調子に乗ってどら焼きを食べてしまいました。
前回とは打って変わっての回復の速さです。
でも、さすがにどら焼きはちょっと早かったようで、おなかがいっぱい。
夜ごはんは、ほんの少量にしました。
法事の後の食事が心配だった嘔吐後4日目
4日目は夫の実家の法事でした。
梅エキスと爪楊枝を保冷バッグに入れてゴー!
行きの車中でムカムカしてきた私と娘(車酔い)は、梅エキスを舐めてスッキリ。
法事も無事に終わり、会食も、普通でも多いわ・・・という量でしたが、1品以外はなんとか完食!
さすがに夜ご飯は抜きましたが、嘔吐4日目でこんなに食べられるなんて、前回のことを思うと信じられません。
吐く回数が少なかったとはいえ、これは絶対梅エキスの効果だと思いました。
2回目は下痢にはならなかったの?
1回目と2回目を一通り見てきましたが、2回目は嘔吐だけ?と思われた方もおられるかもしれません。
実は私、12月と6月の2回の嘔吐の間の4月に、カンピロバクターもくらっていました。
(特におなかが弱いタイプではないのですが、この半年はなんだかいろいろありました)
その時は嘔吐はなく、腹痛と下痢。
6月の嘔吐の頃も、下痢ではないけどおなかはゆるく、まだ本調子ではなかったんですね。
そのため、今回の嘔吐と下痢についての関係ははっきりわからないですが、梅エキスを舐め始めて約3週間くらいから、便の方もやっと整ってきました。
胃腸炎で梅エキスを服用したタイミング
今回の嘔吐後、私が梅エキスを服用したタイミングは以下です。
- ムカムカした時
- おなかが痛いとき
- 思いついたとき
吐いた後とその翌日は食べられなかったので、空腹時は避けるとおいうことはせず、気になったときに舐めていました。
腹痛がひどく、そのままだと刺激が強すぎる気がするなと思ったときは、次に紹介する方法で、飲んでいました。
梅エキスがすっぱすぎて舐めにくいときは
すっぱさ最強の梅エキス。
胃が痛いときなどは、刺激が強すぎるかも?と不安になります。
それ以外にも、子どもは特に、そのままだと飲みにくいですよね。
そんな時は、東城百合子さんの本にも載っていた、はちみつとお湯と梅エキス混ぜるという方法で飲みました。
一回の梅エキスの量
ところで、梅エキスの一回量ってどのくらいでしょうか?
東城百合子さんの本には、以下のように書かれています。
量は大豆一粒か二粒くらい飲めば十分です
「家庭でできる自然療法 誰でもできる食事と手当法」 東城百合子より
ネットのレビューなどを見ていると、爪楊枝の先に少しつけて舐める、お箸の先に少しつけて舐めるなど、もっと少ない量を書いておられる方が多かったです。
私は、大豆一粒はすっぱすぎてムリなので、お箸の先を3ミリほど梅エキスに突っ込み、引き上げたときについている分を一回量としていました。
半年に2回の嘔吐で感じた梅エキスの効果まとめ
1回目と2回目では、嘔吐の回数が違っていたので、単純な比較にはならないかもしれません。
でも、1回目の病院のお薬よりは、2回目の梅エキスの方が、胃腸には効いたような気がしました。
そしてもうひとつ。
これは、もしかしたら、単純に体調が悪くなることで休みが取れた結果なのかもしれませんが、
フラフラするめまいが軽減されてきているように感じます。
梅エキスの効果や使い方についてのまとめです。
- 嘔吐からしばらくは、おなかの調子が悪いなという時には回数は関係なく舐めていました。
- 胃に刺激的過ぎるかも?と思うときは、はちみつとお湯を混ぜて飲みました
- 落ち着いてからも1日に1回は舐めています
- めまいが軽減しているのは梅エキスのおかげかも?
作ってみたかったものの、すりおろすのが大変そうで抵抗があり、なかなか一歩を踏み出せませんでしたが、ブレンダーでの作り方が紹介されていたことで作ることができました。
作って実際に試してみた結果は、作ってよかった!です。
市販でもたくさんの梅エキスがあるので、梅の季節がくるまで待てない!という方は、一度試してみるのもいいかもしれませんね。
梅エキスを作った記録は以下の記事にまとめています。
梅の季節が近付いてきたら、参考にしていただければ嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。